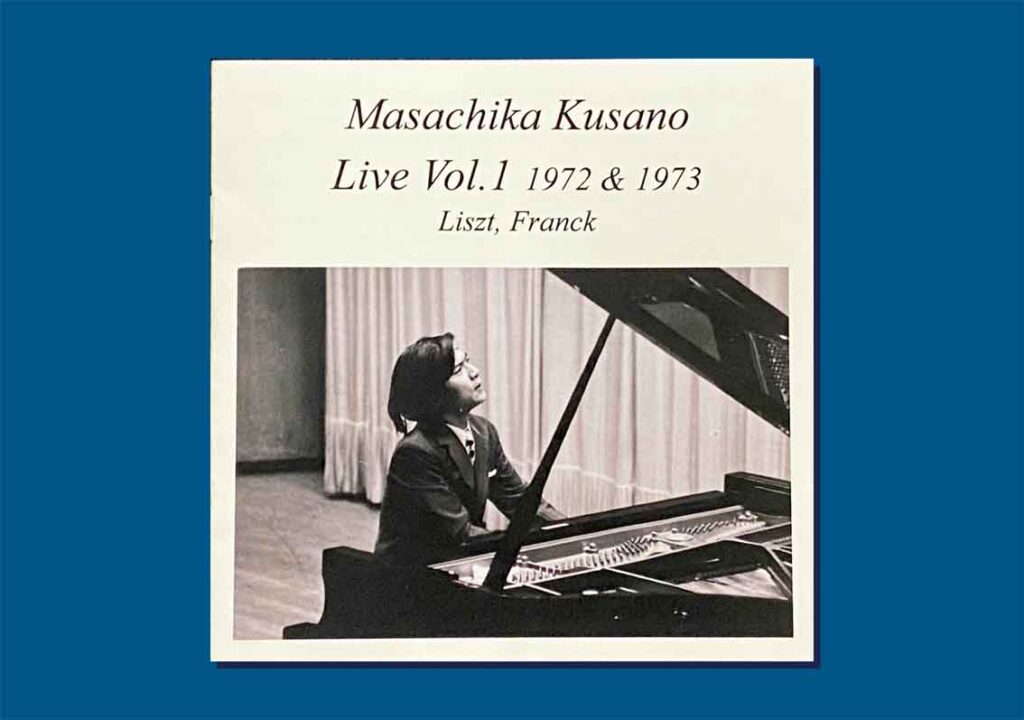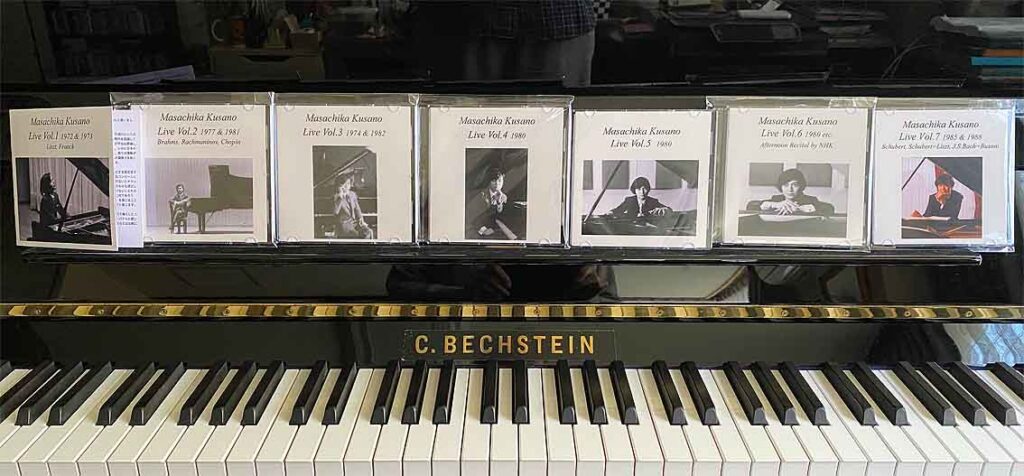すこし前、Eテレでネルソン・ゲルナーのソロによる、ラフマニノフのピアノ協奏曲第3番が放送されました。
指揮はファビオ・ルイージ、NHK交響楽団。
ネルソン・ゲルナーは1969年アルゼンチン生まれのピアニスト。
若いころ、コンクールにおいてもラフマニノフのピアノ協奏曲第3番を弾いて制覇したかったとかで、彼にとってこの作品には並々ならぬ思いがあることを冒頭インタビューで語られていました。
こう聞くと、さてどんな演奏になるのだろう?と好奇心をもってしまいます。
果たして、それは、当世風に注意深い、端正で、嫌味も冒険もないクリアな演奏で、立派な演奏だったとは思うけれど、この作品にとってはいささか物足りないものが残りました。
オーケストラの短い序奏のあとに入る冒頭のシンプルなユニゾンのところは、普通ならだいたい同じようなものだけれど、はやくも表情が凝らされており、いちいちに強弱や呼吸のついたものであったことは、大河が流れるようなスタイルでないことを予感させ、それはある程度当たってました。
もちろん、演奏は十人十色だから「これはこれ」だと思うし、とりわけピアニストのキャリアとともに存在した作品ということで、よく弾き込まれた安心感のようなものもあり、しっかりした演奏だったと思います。
それでも、この曲でどうしても期待するのは、雄渾なスケール感や、深く切ない郷愁、さらにそこへたたみかけてくるピアノの絢爛たる技巧の妙味だろうと…古いかもしれないけれど思うのです。
知的で誠実な演奏であったと言い換えることもできるでしょうが、枠の中にきちんとに収まっている感じが拭えず、少しぐらいはみ出しても構わないから、もっと率直で大胆であってほしいとは思いました。
ゲルナー氏の演奏は、端正で一音一音を決して疎かにしないものでしたが、どこかまとまり過ぎて巨きさがなく、ロシアというよりはヨーロッパの小ぎれいな小国といったイメージでした。
個人的には、ラフマニノフの3番を聴くなら、やはりダイナミックで少々破天荒なぐらいな演奏を求めてしまいます。
だからといって粗暴な演奏では困るけれど、少なくともピアニストの湧き上がる血潮と腕っ節で、燃え盛るような一期一会的な演奏、その陰に見える哀しみ、もっといえば無頼で少しぐらい崩れてもいいから、なにか大きなものを聴かせてもらえるほうが、この作品では大事ではないかと思います。
私だけではなく、多くの人もそうではないかと思ったのは、ワッと襲いかかるような拍手はおこらず、あくまで通常あるような拍手で、それがアンコールとなるまで続いたことでした。
アンコールはリラの花でしたが、これも同様で、表情を入れすぎるのか流れが停滞してしまいます。
ラフマニノフはこまかく考えて台本的に弾くより、もっと本能に任せて、ストレートに現場感をもって弾いてほしいなあと思います。
冒頭インタビューのBGMにはラフマニノフの同曲の演奏が少し流れましたが、見事に自由で必然的な呼吸感のある演奏で、ため息が出るし、聴く方もだいいち楽ですね。
ゲルナー氏いわく、大家の演奏を聞くことには落とし穴があり、模倣に陥ることを警戒しながら自分の演奏を作り上げて行かなくてはならず、ラフマニノフの演奏に近づけたと思っても次のステージではリセットし、常に自由な発想で作品と向き合いたいというようなことを語っていましたが、裏を返せば、模倣しようと思えばできるし、しばしばラフマニノフに迫る演奏をしているんだといわんばかりで、どこか回りくどい宣伝か言い訳のようにも取れました。
せっかく立派な演奏をしているのだから、このようなトークは却って自分の演奏に小さなキズをつけることにならないかと、こちらが心配してしまいますが、まあそれは余計なお世話というものかもしれません。